「遺品整理で起業したいけど、手順や必要な資格がわからない」
「遺品整理業で開業した後、どうやって集客すれば良いのだろう」
遺品整理市場は拡大を続けており、今後も高齢者の増加に伴い需要が高い仕事です。
しかし、需要が高いからといってすぐに開業できるわけではなく、必要な設備や準備、集客のノウハウが必要となります。
この記事では、遺品整理業界の需要と市場規模、起業ステップや起業の方法、必要な資格や集客の方法について紹介します。
目次
遺品整理業界の需要と市場規模

「そもそも今、遺品整理業界で起業して成功できるか」とお悩みの方もいるでしょう。
結論からいえば遺品整理業界の市場規模は拡大傾向にあります。
これは日本の少子高齢化の進行から高齢者の人口が増加していることが関係しています。
統計からみた我が国の高齢者によると日本の高齢者人口は総人口に占める割合は29.1%とかなり高い割合です。
さらに、単身高齢者世帯も増加しており、独居の高齢者が死亡した際に遺品を受け継ぐ人がいないケースが増えています。
遺品整理をする人がいなければ、必然的に遺品整理業への依頼は増加するでしょう。
日本の少子高齢化の進行は喜ばしいことでない反面、遺品整理業界でこれから起業しようとする方にとっては、追い風が吹いている状態ともいえます。
遺品整理事業の起業ステップ

遺品整理事業を起業するステップを簡単に説明します。
- ステップ1.事業計画を立てる
- ステップ2.法人の設立・許認可を取得する
- ステップ3.設備やスタッフを確保する
- ステップ4.集客施策を実施する
ステップ1.事業計画を立てる
遺品整理業を立ち上げる際はまず、事業計画を立てましょう。
具体的には今後5年間の売り上げ目標や想定されるコスト、得られる利益をまとめてください。
計画表の作成により経営の指針が固まり、起業後に計画と照らし合わせて経営状況を確認しやすくなります。
ステップ2.法人の設立・許認可を取得する
遺品整理業での開業に先駆けて、法人を設立しましょう。
法人設立には会社概要の策定や資本金の準備をし、その後法務局へ必要書類を提出して法人登記、資本金の振り込みなどを行います。
会社の形態によって必要な書類や手続き期間は異なりますが、合同会社の場合概ね2週間程度、株式会社の場合は3週間程度が一般的です。
なお、遺品整理での起業は原則資格がなくても可能です。
しかし、遺品整理に伴う不用品の廃棄物処理など付随業務を遂行するには、以下のような認可が必要となるため、業務上必要な資格があれば取得しておきましょう。
ステップ3.設備やスタッフを確保する
遺品整理業に必要な設備やスタッフの確保も欠かせないステップです。
具体的には、以下のような設備を用意しましょう。
- 遺品の運搬に使用する車両(トラック等)
- 防護具(自宅の清掃等に必要)
- 清掃道具(遺品整理及び自宅の片付けをする際に使用)
- 梱包材(遺品の整理や郵送時に必要)
遺品整理を実施するスタッフの確保も必要となるため、求人サイトなどに求人情報を掲載して人を募っておきましょう。
ステップ4.集客施策を実施する
遺品整理の会社を立ち上げても、自動的に仕事が舞い込むわけではありません。
新規立ち上げの業者は認知度が低いため、積極的に集客施策を実施する必要があります。
例として、以下のような施策を実施して自社の存在を広く認知してもらいましょう。
- 会社ホームページの作成
- SNSでの宣伝
- チラシの配布
- 知り合いへの起業のお知らせ
遺品整理で起業する2つの方法

ここまで遺品整理の会社を起業したい人向けに、ステップを説明しました。
しかし「ここまでたくさんのことを自分でできるか」と不安な方もいるはずです。
そのような方のために、遺品整理で起業する方法をより詳しく説明します。
- フランチャイズで起業する
- コンサルを受けて自力で起業する
- 1から自力で開業する
フランチャイズで起業する
大手遺品整理業の会社とフランチャイズ契約を結んで、起業する方法があります。
加盟店という位置付けで大手遺品整理業者から顧客を紹介してもらい、起業に関するサポートを受けられるのがメリットです。
親会社が大手であるほど知名度も高く顧客からの信頼も厚いため、立ち上げ当初でも仕事を受けやすくなります。
また、親会社で所有しているノウハウを共有してもらえるため、効率の良い業務フローや集客方法についても学べる点がメリットです。
デメリットとしては、加盟店になるにあたって発生する加盟金や手数料が発生することです。
また、親会社が定めたルールには原則従う必要があり、店舗オーナーの意見がやや通りにくく自由な経営ができない可能性があります。
とはいえ、遺品整理業者が増えている中で、一から起業して集客を実施するのは大変です。
大手の力を借りて自社でノウハウを蓄積するためにも、立ち上げ当初は特にフランチャイズ加盟をおすすめします。
コンサルを受けて自力で起業する
フランチャイズに抵抗があるという方は、遺品整理業のコンサルタントを利用するのがおすすめです。
遺品整理業の企業や経営に知見の深いコンサルタントから、起業アドバイスや経営ノウハウ、集客の方法についてのアドバイスを受けられます。
コンサル料はかかりますが、フランチャイズのようにロイヤリティを支払う必要がなく、契約期間が終了したあとは費用がかかりません。
起業サポート、集客のみなど範囲を絞ったコンサル依頼も可能なので、費用を抑えたい方は自社で自信がない部分のみコンサルからノウハウを提供してもらうと良いでしょう。
また、資金にある程度余裕がある場合は、起業サポートから集客、経営改善の総合コンサルティングもおすすめです。
1から自力で開業する
初期費用を抑えたいという方は、一から自力で起業する方法もあります。
遺品整理業の開業にかかる費用のみで起業でき、最も初期費用を抑えられる方法です。
ただしこの方法は、すでに遺品整理業者で勤務経験があり、ノウハウやコネクションがある方向けです。
費用は安いものの、起業や運営に関するアドバイスがなく、集客も自身で行うとなるとタスク量は膨大なものとなります。
遺品整理業に知見が深く、起業についても知識がある方以外はフランチャイズまたはコンサルタントの利用を検討した方が良いでしょう。
遺品整理で起業する人が知っておきたい収益モデルと仕事内容

遺品整理での独立を考えている方が覚えておくべき収益モデルと仕事内容を解説します。
今まで遺品整理の仕事の経験があっても、自分で経営をするとなると話は別です。
改めて収益モデルや仕事の内容を整理し、事業計画の策定に役立ててください。
- 遺品整理業の収益モデル
- 遺品整理で起業する人の仕事
遺品整理業の収益モデル
まず遺品整理業の収益モデルについて解説します。
サービスの提供で得られる収益とコストについて紹介するので、自社でどのようなサービスを提供するかも含めて検討しましょう。
| 遺品整理の収益モデル |
| 基本料金 |
| 追加オプション |
| 廃棄物処理料金 |
| 買取収入 |
| 遺品整理業でかかるコスト |
| 人件費 |
| 設備・車両費 |
| 廃棄物処理費用 |
| マーケティング費用 |
| 各種保険料 |
一般的に遺品の片付け1件あたりの売り上げは10〜30万円程度、経費はおおよそ半分といわれています。
つまり、1件遺品整理の依頼があれば5〜15万円の収益を上げることが可能です。
月に10件程度の依頼があれば、50〜150万円の収益が期待できます。
さらに、これに加えて遺品を買取して販売する収益などが加われば、さらに収益を上げられます。
遺品整理で起業する人の仕事
遺品整理業といっても、単に遺品の片付けだけを生業としているわけではありません。
遺品整理業者の多くは、以下のような依頼に幅広く対応しています。
- 遺品と不用品の仕分け
- 不用品回収や廃棄
- 不要な家財の買取や搬出
- 清掃作業
- ハウスクリーニング
- 遺品の供養
- 空き家の売買
- 解体
先ほども紹介した通り遺品の片付け単体での依頼で得られる利益は、1件5〜15万円程度です。
経費が半分程度かかることを考えると、遺品整理以外のオプションやサービスを提供し、収益性を高める必要があります。
遺品以外にも家じまいの手伝いとして家財の処分や買取をおこなったり、空き家の解体や売買などまでサービスの幅を広げることで、より収益を確保して安定した経営が可能です。
遺品整理業の起業に必要な資格と認可|取得方法も紹介

遺品整理業の起業にあたり、必要となる資格と認可、その取得方法を説明します。
- 遺品整理士
- 古物商許可
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- その他取得しておくと役立つ資格
遺品整理士
| 資格の種別 | 民間資格 |
| 資格認定を行う機関 | 一般財団法人遺品整理士認定協会 |
| 取得方法 | 養成講座の受講・レポート提出 |
| 取得期間の目安 | 2ヶ月 ※レポート提出期限は無料で延長可能 |
| 取得にかかる費用 | 入会金:25,000円 会費:10,000円(認定費用含む) |
遺品整理士とは一般財団法人遺品整理士認定協会により設立された民間資格です。
民間資格といえど業界では知名度と信頼性の高い資格であり、その会員数は6万人を超えています。
取得により遺品の片付けに関する基礎や供養、廃棄物やリサイクルについての知識など、遺品整理に欠かせない知識を体系的に学べます。
遺品整理士の資格取得には、一般財団法人遺品整理士認定協会の養成講座に申し込み、過程終了後のレポート提出が必要です。
レポートの内容を遺品整理士認定協会にて採点し、合格すれば遺品整理士を名乗れます。
古物商許可
| 届出の提出先 | 管轄の警察署 |
| 取得方法 | 申請書及び必要書類の提出 |
| 取得期間の目安 | 40日程度 |
| 取得にかかる費用 | 19,000円 |
古物商許可とは、中古品の売買を事業としておこなう際に必要な許可です。
遺品整理業として遺品の買取や販売をする際には必須となります。
古物商許可は管轄の警察署へ申請書を提出し、受理番号が発行されることにより営業が可能となります。
古物商許可の届出には専用の書式と以下の添付書類が必須となるため、抜け漏れのないように揃えておきましょう。
<添付書類>
法人許可申請の場合
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
- 略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
引用:古物商許可申請 警視庁」
なお、申請には19,000円の手数料が必要です。
申請から受理番号の発行まで40日程度かかるケースが多いため、早めに申請を出しておきましょう。
産業廃棄物収集運搬業許可
| 届出の提出先 | 都道府県知事 |
| 取得方法 | ・産業廃棄物の収集・運搬課程(新規)の受講 ・都道府県への申請 |
| 取得期間の目安 | 40〜90日程度 |
| 取得にかかる費用 | 【受講費用】 収集運搬許可の場合 対面:29,700円 オンライン:25,300円【申請費用】 81,000円(全国一律) |
産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物を運搬して廃棄するために必要な資格です。
資格取得までの期間が長く、最短で40日間、最長で3ヶ月程度かかる場合があります。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するにはまず産業廃棄物の収集・運搬課程(新規)の受講が必要です。
対面とオンライン2つの受講方法を選択できますが、費用が安いオンラインでの受講をおすすめします。
受講後は都道府県に必要書類を提出し、認可が下りるのを待ちましょう。
必要な書類は各自治体によって変わる可能性があるため、管轄の自治体の書類を確認して必要書類を揃えましょう。
例として東京都での産業廃棄物の収集運搬業許可申請に必要な書類を紹介します。
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証
- 事前計画書(収集運搬業積替え保管施設用)
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 変更事項確認書・新旧役員等対照表
- 事業計画の概要
- 運搬車両(又は船舶)の写真(カラー)
- 運搬容器等の写真(カラー)
- 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
- 誓約書
- 最新の定款の写し
- 法人の登記事項証明書
- 住民票抄本
- 成年被後見人等に該当し ない旨の登記事項証明書 等
- 政令使用人に関する証明書(当該使用人がいる場合)
- 申請者の許可証の写し
- 貸借対照表(直近3年分)※設立したばかりの場合は開始貸借対照表を提出
- 損益計算書(直近3年分)※設立したばかりの場合は不要
- 株主資本等変動計算書(直近3年分)※設立したばかりの場合は不要
- 個別注記表(直近3年分)※設立したばかりの場合は不要
- 所得税の納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)※設立したばかりの場合は不要
- 経理的基礎を有することの説明書(p.30)及び記載者の資格証明書、又は返済不要 な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類(任意書式)
- ICタグ付き自動車検査証の場合は自動車検査証記録事項の写し、従来の 自動車検査証の場合は車検証の写し(使用する全車両)
その他取得しておくと役立つ資格
必須ではありませんが、遺品整理業で起業する際に取得しておくと役立つ資格を紹介します。
| 終活カウンセラー | 相続や遺言、葬儀や遺品整理などについて総合的にシニアの悩みに寄り添い、解決する役割が果たせることを証明する資格。 |
| 遺品供養士 | 遺品整理や供養、遺族のグリーフケアの業務ができる知識があることを証明する資格。 |
| 生前整理アドバイザー | 生前整理に伴う清掃や片付けなどのノウハウを学び、生前整理についてのアドバイスができることを証明する資格。 |
| グリーフケアアドバイザー | 家族を亡くした遺族の悲しみに寄り添い、心のケアができることを証明する資格。 |
| 相続診断士 | 相続資産に関しての相談を受け、事前にトラブルがあれば顧客へ報告し、円滑に相続が完了するようにサポートできることを証明する資格。 |
生前整理や遺品供養、遺族のグリーフケア、相続など遺品整理と関わりの深い資格を取得することで、顧客からの信頼度が上がり、集客にも役立ちます。
また、提供できるサービスの幅を広げられるため、遺品整理業としての収益アップも期待できるでしょう。
遺品整理の起業にかかる資金

遺品整理の起業にかかる資金を心配している方もいるはずです。
以下3つのパターンに分けて、遺品整理の起業に必要な資金を解説します。
- フランチャイズで起業する場合の費用
- コンサルを入れて起業する場合の費用
- 自力で起業する場合の費用
フランチャイズで起業する場合の費用
フランチャイズで遺品整理業を起業する場合にかかる初期費用は、100〜200万円程度が一般的です。
加盟金に加えて保証金や研修費用などの初期費用が含まれるため、初期費用はやや高額になります。
ただし、加盟する企業により加盟金や保証金はまちまちであるため、事前によく費用を比較しておくと良いでしょう。
さらに起業後には毎月収益の5〜7%、または月に数万円程度のロイヤリティが発生する可能性があります。
コンサルを入れて起業する場合の費用
コンサルを入れて起業する場合にかかる費用もフランチャイズと同じくらいです。
起業サポートから経営ノウハウまでの総合コンサルの場合はコンサル料がかかりますが、集客ノウハウのみのコンサルであれば比較的安価で済むなど、サポート範囲によって費用が変わります。
コンサル料は依頼するコンサルタント会社によって費用の幅があるため、利用する前にコンサル費用を比較しておくと良いでしょう。
自力で起業する場合の費用
完全に自力で起業する場合の費用は100万円程度で、コンサルやフランチャイズよりも安価に起業できます。
特に車両などの設備をすでに持っている、または安く譲ってもらえるなどの場合は、コストを下げて起業が可能です。
ただし、立ち上げた直後から事業が安定するとは限らないため、初期費用が抑制できても経営が成り立たない可能性がある点に注意しましょう。
遺品整理の起業で活用できる助成金

遺品整理の起業にかかる費用が高く、不安を感じた人は助成金の利用を検討しましょう。
以下のような助成金を利用すれば、遺品整理業の起業コストを抑えられます。
| 創業促進補助金 ※自治体ごとに設置 |
起業する人に対しての補助金 東京都の場合は下限100万円〜400万円 |
| 地域中小企業応援ファンド | 中小企業の創業者に対して資金を支援するファンド |
| 特定求職者雇用開発助成金 | 高齢者や障害者などの就職困難者を継続的に雇用する場合の助成金 |
| 雇用調整助成金 | 経済上の理由により事業縮小を余儀なくされた場合に、雇用者への休業手当、賃金などに対しての助成金 |
| 労働移動支援助成金 | 事業縮小が理由で離職を余儀なくされる雇用者に対しての再就職支援、雇い入れで受けられる助成金 |
| キャリアアップ助成金 | 非正規雇用労働者をキャリアアップさせて正社員として雇用する、または処遇改善の取り組みを実施することで受けられる助成金 |
起業に関する補助金としては、各自治体の創業促進補助金(名称は自治体により異なります)を利用すると良いでしょう。
枠が限られており、予算上限額を超えると募集が終了してしまうというデメリットはあるものの、選定されれば数百万円の補助を受けられる制度です。
その他、遺品整理の起業で活用できる助成金として、雇用支援に関するものが多いです。
障害者や高齢者、離職者に対しての支援を実施することで助成金がもらえる制度も活用しましょう。
遺品整理で起業したあとの集客方法

遺品整理業で起業したあとに、すぐに仕事が舞い込むと期待してはいけません。
立ち上げたばかりは実績も口コミもなく、顧客からの信頼が得にくい状態です。
以下のような方法を駆使して自社をPRし、より多くの人から遺品整理の依頼が入るようにしましょう。
- 自社ホームページからの集客
- 業者紹介サイト
- チラシや不動産業との提携
自社ホームページからの集客
遺品整理で起業した後は、自社ホームページを制作して集客しましょう。
ホームページがない業者はサービス内容や口コミが確認できないため、顧客からの信頼感を得にくいです。
また、ホームページの制作により、遺品整理業者を探している人が自然流入でサイトに辿り着き、依頼を獲得できる仕組みを構築するためです。
最初のうちは検索エンジン上位に自社ホームページが表示されにくいですが、SEO対策を実施することで徐々に流入が増えてきます。
ホームページ制作は難しそうなイメージがありますが、簡単に作成できる「ペライチ」のようなサービスを利用する方法もあります。
また「Wordpress」というツールを使えば、体裁の整ったサイトを簡単に制作可能です。
業者紹介サイト
ホームページを作ったら、業者紹介サイトにも登録しておきましょう。
遺品整理業者を紹介するサイトへ自社情報を登録することで、遺品整理業者を探している人とマッチングしやすくなります。
サービス立ち上げ直後は、顧客からの直接の問い合わせや利用依頼は期待できません。
業者紹介サイトのような集客力の強いサイトへの登録で、効率よく自社サービスを認知してもらい、申し込みに繋げられます。
「みんなの遺品整理」「くらしのマーケット」のような紹介サイトは集客に役立つので、起業してホームページを制作したら、すぐに登録しましょう。
チラシや不動産業との提携
オンラインだけでなく、オフラインでの集客も欠かさないようにしましょう。
遺品整理を利用する方は高齢の方が多く、インターネットが使えない方もいます。
そのような方にはポストへチラシを投函したり、地元の不動産業者と提携して遺品整理を必要としている方を紹介してもらう方法が有効です。
自社サービスをまとめたチラシを作り、該当地域の居住者へポスティングしたり、地場の不動産屋に営業をかけてチラシを置いてもらい、仕事を振ってもらうように営業をかけましょう。
遺品整理の起業を成功させるには

遺品整理の起業を成功させるコツを6つ紹介します。
- 遺族の気持ちに寄り添うサービスを提供する
- 効率の良い業務フローを確立する
- 遺品整理に関連したサービスも展開する
- マーケティングに力を入れる
- 他社との差別化のための教育や研修会を実施する
- フランチャイズやコンサルを利用する
遺族の気持ちに寄り添うサービスを提供する
遺品整理は非常にデリケートな業務であり、単なる不用品回収ではありません。
大切な人を亡くした遺族に寄り添い、丁寧な作業や形見分け、相続に関する問題の解決に向き合う姿勢が重要です。
遺族の気持ちに寄り添ったサービス提供ができてこそ、利用者からの良い口コミを得られ、そこから評判が広がって集客の輪が広がります。
参考までに便利屋サービス21に寄せられた口コミを紹介します。
「東京都八王子市のSです。突然実家の親が亡くなってしまい仕事が忙しく遺品整理の作業の方法が分かりませんでした。そこで遺品整理業者の便利屋サービス21さんに相談したところ遺品整理士の方が親切に相談に乗っていただき、とても分かりやすく教えていただきました。最終的には便利屋サービス21さんに遺品整理と不用品回収と片付けをお願いしました。真心込めて丁寧に作業を行っていただき大変感謝しております。 後日、空き家となった実家の片付け作業もお願いしたいと思います」
「神奈川県横浜市のTです。親族の家が空き家で長年放置してましたが遺品整理と空き家の片付けをしたいと考えており便利屋サービス21さんに相談しました。便利屋サービス21さんに相談したところ、他の遺品整理作業直後であればスケジュールも空いてるのでと、お問合せした日の当日に遺品整理と空き家の片付けの作業に来ていただけました。
全て即日でご対応いただき、また今回手持ちのお金があまりなく分割支払いにてご対応いただき、とても助かりました。」
上記のように丁寧な作業、サービスの幅広さや対応の良さは、必ずお客様に評価してもらえるものです。
遺族が何を必要としているか先回りして考え、遺品整理業者として丁寧なサービスを心がけましょう。
効率の良い業務フローを確立する
遺品整理は遺族の気持ちに寄り添う丁寧なサービスと、効率の良い業務フローを両立させる必要があります。
2つは矛盾するようですが、効率の悪い作業配属に不安を与えるばかりでなく、自社の経営効率を大きく下げてしまいます。
遺品整理の手順や重要書類の探し出しのノウハウなどを学び、遺品の買取や販売のフローを確立するなど、経営における業務フローもよく検討しておきましょう。
遺品整理に関連したサービスも展開する
遺品整理業で起業する場合は、遺品整理にサービスを絞り込まず、関連サービスを展開しましょう。
たとえば、生前整理や終活の相談は遺品整理と関連性が深く、需要の高いサービスです。
また、遺品の買取や供養などが提供できれば、遺族が別で遺品を処分したり供養する手間を省けます。
以上のように遺品整理業で開業する際は、顧客にニーズの高いサービスも展開できるよう準備しておきましょう。
マーケティングに力を入れる
遺品整理業は起業までのステップが多く、起業後に満足してしまう方もいます。
しかし、事業立ち上げ後に自然と顧客からの依頼が入るわけではありません。
集客のためのマーケティングについても勉強し、速やかに実施できるようにしておきましょう。
たとえば、開業前にホームページ制作を済ませておいて同時に公開する、チラシを投函する、事前に不動産会社に根回しをしておくなどのマーケティングが重要です。
また、拡散性の高いX(旧Twitter)などのSNSを使って自社サービスを宣伝する方法もおすすめです。
SNSアカウントはすぐに開設できるので準備しておき、開業日と同時に投稿を始めましょう。
他社との差別化のための教育や研修会を実施する
遺品整理の市場が拡大する中で、今後は遺品整理業での開業者が増えることが予想されます。
遺品整理業は資格がなくても起業できるうえ、資格も独占業務というわけではないため、仕事の内容で差をつけるのは難しいです。
ライバルに対抗するために、他社との差別化施策を考えておきましょう。
たとえば、終活や生前アドバイザーの資格取得者を雇用した独自サービスの提供、遺族のグリーフケアができるなど、付加価値をつける方法がおすすめです。
また、遺品整理と関連する空き家の整理や売却などもワンストップで提供できれば、ユーザーの利便性が上がり依頼が増える可能性は上がります。
付近の業者が提供していないサービスを見つけ出して差別化することで、遺品整理業者としてアドバンテージを勝ち取れるでしょう。
フランチャイズやコンサルを利用する
遺品整理業は起業の時点で準備することが多く、つまずく人が非常に多いです。
無資格で営業できるとはいえ、遺品整理ができるという一点だけでは生き残れません。
また、起業後に集客で苦労する遺品整理業の独立者が多いのも事実。
この問題を解決して安定した経営を目指すには、フランチャイズやコンサルタントの利用をおすすめします。
フランチャイズであれば起業のサポートからノウハウの提供、顧客の紹介までしてもらえるので、起業の苦労を大幅に軽減できます。
ロイヤリティの支払いなどが心配であれば、コンサルタントを入れて企業や集客のアドバイスをもらう方法も良いでしょう。
遺品整理での業務経験があっても、経営となると話は別。
フランチャイズやコンサルタントを頼りながら、経営を軌道に乗せる方が効率が良いはずです。
遺品整理の起業にフランチャイズやコンサルを入れるべき理由

遺品整理の起業にはフランチャイズ加盟、またはコンサルタントの利用がおすすめです。
なぜさらにお金をかけてまでフランチャイズへの加盟やコンサルの利用が必要なのか、その理由を解説します。
- 起業準備からサポートを受けられる
- 遺品整理のノウハウを教えてもらえる
- 集客の苦労を大幅に減らせる
起業準備からサポートを受けられる
フランチャイズやコンサルの利用により、遺品整理業の企業準備からサポートを受けられます。
必要な準備物の確認や各種認可の申請サポートなどをしてもらえるので、自分一人で準備するよりもスムーズに準備が終わります。
また、集客に関してもホームページの制作や集客ノウハウの提供を受けられるため、初めて独立する場合でも効果の高い集客施策のコツを盗める点がメリットです。
遺品整理のノウハウを教えてもらえる
遺品整理の経験者であっても、実際に自分が遺品整理業を運営する際は、経験外の業務が生じるはずです。
遺品整理以外の古物商としての仕事や廃棄物の処理など、覚えるノウハウはたくさんあります。
1から全ての仕事を覚えていくと膨大な時間がかかり、起業が遅れるような事態になりかねません。
その点フランチャイズやコンサルを利用すれば、親会社が所持するノウハウを教えてもらえるため、手順を教えてもらって実行すればすぐに業務を開始できます。
集客の苦労を大幅に減らせる
遺品整理業の起業後に苦労するのが集客です。
業者紹介サイトへ登録してもなかなか問い合わせが入らない、チラシの反響がないと悩む業者は非常に多いのが現実。
そのまま集客がなければ当然無収入となり、雇用したスタッフの給料も払えません。
フランチャイズへ加入すれば親会社からの顧客の紹介を受けられます。
親会社へ問い合わせした顧客を加盟店へ割り振り、仕事を紹介する制度があるためです。
また、集客ノウハウの提供なども受けられるため、完全な独立よりも集客の苦労は減らせます。
遺品整理の起業に関する苦労を全て一人でこなすのは、正直難しいです。
フランチャイズへの加盟やコンサルタントの利用には費用はかかるものの、ノウハウの提供や集客の苦労の軽減など、多大なメリットがあります。
スムーズに遺品整理業を軌道に乗せたいなら、フランチャイズやコンサルタントの利用を検討しましょう。
遺品整理業の起業に関してよくある質問

最後に遺品整理業の企業に関して、よくある質問をまとめました。
- 遺品整理業の起業に資格は絶対に必要なのですか?
- 遺品整理の国家資格はありますか?
- 遺品整理で起業して儲かりますか?年収はいくらくらいですか?
- 一人で遺品整理業を始められますか?
遺品整理業の起業に資格は絶対に必要なのですか?
遺品整理業の起業に必須の資格はありませんが、業務を遂行するうえで産業廃棄物収集運搬許可、古物商の届出はあったほうが良いでしょう。
事前に上記2つの許可は得ておき、遺品整理業開業後にスムーズに業務を開始できる状態を作っておきましょう。
遺品整理の国家資格はありますか?
2024年9月時点では、遺品整理に関しての国家資格は存在しません。
遺品整理で信頼度の高い資格を取得したい場合は「遺品整理士」を取得すると良いでしょう。
遺品整理で起業して儲かりますか?年収はいくらくらいですか?
遺品整理で独立起業した場合の想定年収は600〜1,800万円程度です。
遺品整理だけでなく買取や不用品回収などサービスの幅を広げることで、収益性を高めてより高年収を目指せます。
ただし、集客に失敗して依頼がない場合は無収入になることも覚えておきましょう。
一人で遺品整理業を始められますか?
一人でも遺品整理業は始められますが、遺品の量によっては一人で整理できません。
また、遺品の運び出しなどに人手が必要なので、現実的に考えると一人起業は難しいでしょう。
どうしても一人で遺品整理を始めたい方は、遺品の量が少ない依頼だけ請け負う、運び出しなしで整理のみ手伝うなどサービスの幅を限定して起業してみてください。
まとめ:遺品整理業の起業準備でお悩みなら便利屋サービス21へご相談ください
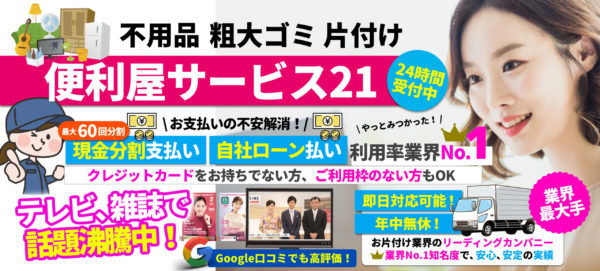
「遺品整理業の起業を考えているが、一人で準備から集客、経営までこなす自信がない」
そんな方は、便利屋サービス21へご相談ください。
便利屋サービス21を運営するBSC合同会社では、遺品整理業の起業支援を実施しています。
フランチャイズへの加盟、起業に関するコンサルタント双方に対応しており、新しく遺品整理業界へ参入したい方を支援いたします。
BSC合同会社は遺品整理をはじめ、不用品回収やゴミ屋敷の片付け、空き家の解体や不動産売却のサポートなど、幅広いノウハウを持つ会社です。
あなたの遺品整理業としての起業を、弊社の豊富なノウハウで支援しますので、ぜひお問い合わせください。












































