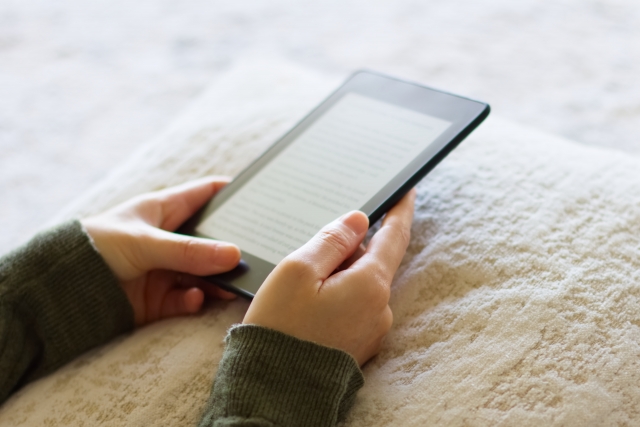「物が捨てられなくて部屋中にゴミが溜まっているけど、片付け方が分からない…」
「思い出の品だから捨てられないのに、もう部屋に置くスペースがない…」
捨てられない人はものがどんどん増えていき、自宅をゴミ屋敷にしてしまうこともあります。
その背景には、様々な心理的要因や社会的な課題が隠れているものです。
この記事では、ゴミ屋敷の住人が物を捨てられない理由と、その解決方法について専門家の視点から解説します。
目次
ゴミを捨てられない人の特徴とは

物が捨てられない方には、いくつかの共通する特徴があることが分かっています。
①カバンが物でぱんぱん
物を捨てられない方のカバンの中を見ると、必要以上の物が詰め込まれていることが多いです。
普通なら捨てるはずの古いレシートや使い終わったティッシュ、不要なパンフレットなどがそのまま残されています。
このような方は「いつか必要になるかもしれない」という考えから、日常的に使わないものまでカバンに入れたままにする傾向があります。
実際に片付けを依頼されるお客様の多くは、初回訪問時にカバンからものを取り出す際に、何年も前のレシートや使用済みのティッシュが出てくることがあります。
②周囲と関わりがなく孤独である
ゴミ屋敷の住人の多くは、家族や友人、近所の方々との交流が少ない傾向があります。
社会から孤立した生活を送ることで外部からの刺激や指摘が減り、自分の生活環境に対する客観的な視点を失いがちです。
「誰も来ないから」という理由で片付ける必要性を感じなくなってしまい、次第に物が溜まっていきます。
また、人間関係の希薄さが寂しさを生み、その埋め合わせとして物への執着が強まるケースも少なくありません。
③意外と女性に多い
一般的なイメージとは異なり、ゴミ屋敷の住人には女性が一定数いるといわれています。
特に単身女性に多く見られ、その女性には思い出の品への執着が強い傾向が見受けられます。
女性は男性に比べて情緒的な価値観を大切にする傾向があり、物に対する思い入れが強くなりやすいからです。
例えば、子どもの頃の写真や手紙、亡くなった家族の遺品など、思い出が詰まった品々を手放せないケースは多いです。
また、「いつか使うかもしれない」という考えから、古い衣類や調理器具、雑貨などを大量に保管し続ける傾向も女性に多く見られます。
女性が意外にゴミ屋敷が多いという論点についてまとめたゴミ屋敷になる女性の心理と特徴!予防策とゴミ屋敷の解決法も解説もぜひお読みください。
なぜゴミ屋敷になってしまうのか?捨てられない理由

ゴミ屋敷になってしまう原因は一人一人異なりますが、その背景には共通する要因があります。
捨てられない理由を知るために、自分の環境と照らし合わせてみましょう。
1. 多忙による体力や気力の低下
毎日の仕事や家事に追われ、帰宅後は疲労困憊で片付ける気力が残っていない状態が続くと、徐々に家が汚くなっていきます。
今日は疲れたから明日やろう」という思いが積み重なり、気づけば片付けられないほどのゴミが溜まってしまうからです。
特に単身世帯では、他の家族からの指摘や協力がないため、状況が悪化しやすい傾向があります。
また不規則な勤務形態の場合、生活リズムが乱れ、片付けの習慣が身につきにくいのも原因の1つです。
さらに、労働環境の悪化から疲労状態が続くと判断力が落ちて、何をどう片付けて良いか分からなくなってしまいます。
2. 物への強い執着心(「もったいない」症候群)
「もしかしたら将来使えるかもしれない」という考えから、不用品を手放せなくなる心理が働きます。
例えば、古い雑誌や新聞を「いつか読み返すかもしれない」と何年も保管し続けたり、壊れた電化製品を「修理して使えるかもしれない」と取っておいたりします。
また、セールやキャンペーンで安く手に入れた商品、もらい物などは特に捨てにくく、使わないまま保管され続けることも多いです。
この「もったいない症候群」は日本人に特に強く見られる傾向があります。
物の価値を金銭的な面だけでなく、感情的な面からも判断してしまうことから、合理的な整理整頓が難しくなってしまうのです。
3. 孤独感を物で埋めようとする心理
現代社会では、高齢者の独居世帯や単身世帯が増加し、人との関わりが希薄になっている傾向があります。
家族や友人、近隣住民との交流が少なくなると、心の空白を物で埋めようとする心理が働きます。
「この品物は○○さんからもらったもの」「あの時の思い出が詰まっている」など、物に対して強い感情的な価値を見出すようになります。
孤独感が強まるほど、物への執着も強くなり、手放すことに強い抵抗を感じるようになるのです。
特に高齢者や配偶者を亡くした方は、過去の思い出が詰まった品々を捨てることで、大切な思い出を捨てるような感覚になり、より一層物が捨てられなくなります。
4. 汚れた環境に無関心
ゴミ屋敷の住人も、最初は「片付けなければ」と思っていても、少しずつ物が増えていく中で、その状態が「普通」だと感じるようになります。
一週間に一つずつ物が増えていくように緩やかに環境が変わるので、本人が状況の悪化に気づきにくく、気づいた時には既に手に負えない状態になっていることが多いです。
また、ゴミが溜まった環境に慣れてしまうと、悪臭や不衛生な状態にも鈍感になり、健康上のリスクに気づかなくなってしまいます。
さらに、長期間にわたって汚れた環境で生活していると、「もう元には戻せない」という諦めの気持ちから、さらに片付ける意欲が低下することもあります。
5.ストーカー被害などによるトラウマ
過去にストーカー被害を受けた方などは、そのトラウマからゴミ捨てができなくなり、家にゴミを溜め込んでしまう傾向があります。
例えば、出したゴミを漁られて個人情報を悪用されたり、プライベートを詮索された経験から、ゴミ出し自体が怖くなってしまいます。
また、過去にゴミの分別で厳しく注意を受けた経験から、ゴミの分別に自信をなくし、ゴミ出しが億劫になる人もいるでしょう。
このように過去に受けたなんらかのトラウマから、ゴミを出せない人もいます。
病気が原因で捨てられなくなっている事例

物が捨てられない人の背景には、医学的な問題が隠れていることがあります。
これらの症状は単なる「怠け」や「だらしなさ」ではなく、病気が原因なので適切な治療やサポートが必要です。
ケース1:発達障害(ADHD・アスペルガー症候群)
発達障害は先天的な脳の機能特性であり、注意欠如・多動性障害(ADHD)や自閉スペクトラム症(アスペルガー症候群を含む)などが物の整理整頓に影響を与えることがあります。
ADHDがある方は、整理整頓や物事の優先順位付けが苦手な傾向があり、「片付けよう」と思っても注意が散漫になり、最後まで作業を完了できないことがあります。
また、「あとでやろう」という先延ばし傾向も強く、結果として物があふれる状態になりやすいのです。
自閉スペクトラム症の特性を持つ方は、特定の物へのこだわりが強かったり、物の分類や処分の判断が難しかったりすることがあります。
例えば、特定のジャンルの本や雑貨を大量に集めてしまったり、「正しい」分類方法にこだわるあまり、他の人から見たら「部屋が散らかっている」という状態になりがちです。
アスペルガー症候群とゴミ屋敷の関係はアスペルガー症候群の人がゴミ屋敷になりやすい理由と対策を解説!をご覧ください。
ケース2:強迫性障害
強迫性障害は、「意味がない」と分かっていても、特定の考えや行動から逃れられなくなる精神疾患です。
「捨てたら不安」「何か悪いことが起こるかもしれない」といった強迫観念に囚われ、物を手放せなくなることがあります。
例えば、レシートや領収書を捨てると「後で必要になったときに困る」という不安が強まり、何年分も保管し続けてしまうケースや、新聞や雑誌を「読み終わっていない」という理由で大量に溜め込むケースなどがあります。
強迫性障害による溜め込みの特徴は、捨てることへの強い不安と恐怖感を伴うことです。
物を捨てようとすると、極度の不安や恐怖、時には動悸や発汗などの身体症状が現れることもあります。
ケース3:ためこみ症(溜め込み症)
ためこみ症の特徴は、実際の価値に関わらず物を捨てることが困難で、生活空間が物で埋め尽くされてしまうことです。
ためこみ症の方は、一般的に価値のない物にも特別な意味や価値を見出し、将来使う可能性や愛着を理由に手放せなくなります。
また、自分の持ち物の位置や内容を正確に把握したいという強い欲求があり、他人が片付けることに強い抵抗を示すことも特徴です。
さらに問題なのは、ためこみ症の方は自分の状態に気づきにくく、周囲が指摘をしても改善しようという意向を示さないことです。
治療には、認知行動療法的アプローチが有効で、カウンセリング等を通して認知の歪みを正していく必要があります。
ケース4:うつ病や認知症などの疾患
うつ病や認知症などの精神疾患も、物が捨てられない状態の背景要因となることがあります。
うつ病の方は、気力の低下や意欲の減退により、日常的な片付けや掃除ができなくなることがあるでしょう。
「何をするにも疲れる」「何も手につかない」という状態が続き、ゴミを捨てる簡単な作業さえも大きな負担に感じるようになります。
認知症の場合は、判断力や遂行機能の低下により、何を捨て何を残すべきかの判断が難しくなります。
さらに、物の管理や整理整頓に関する記憶や能力が失われても、「物を取っておく習慣」だけは残ることがあり、ゴミ屋敷になる場合もあります。
高齢者宅がゴミ屋敷化しやすい理由は?家が荒れる前後の対策を解説では、認知症についても詳しく説明しています。
【補足】専門医に相談すべき症状に注意
これまで紹介した病気が原因で物が捨てられず、自宅がゴミ屋敷になっているなら、専門医に相談が必要です。
特にトイレやお風呂が使えず日常生活に支障が出ていたり、家族が片付けようとすると激怒したり、暴れたりするような方を放置してはいけません。
症状が悪化すると部屋がゴミ屋敷になるだけでなく、精神的な病による自傷や他害などのリスクが発生する可能性があります。
本人のためにも周りの方のためにも、少しでも「おかしいな」と思うところがあれば、医療機関に相談しましょう。
ゴミ屋敷の不用品を捨てられない人は周りの人を頼ろう

捨てられないことが原因で部屋がゴミ屋敷になってしまったら、まず周りの人を頼りましょう。
「こんなこと誰に相談したら良いの」という方向けに、頼るべき人の詳細について説明します。
家族や友人
家族や友人は身近な分、悩みを打ち明けやすい存在です。
特に片付けや整理整頓が得意な人がいれば、具体的なアドバイスをもらえる可能性があります。
一緒に片付けを手伝ってもらえば、自分では捨てられない物も客観的な意見をもらいながら整理できるでしょう。
ただし、身近だからこそ言いづらいという方もいるでしょう。
そういった場合は、次で紹介する行政サービスや専門業者を頼ることも検討してみてください。
行政の支援サービス
高齢の方が独居している場合など、自治体によってはゴミ出し支援サービスを提供していることがあります。
例えば、玄関先までゴミを持ってきておけば回収してくれる「ふれあい収集」などのサービスです。
また、最近では「ゴミ屋敷条例」を制定している自治体も増えており、清掃費用の一部補助や相談窓口の設置など、様々な支援策を講じています。
まずはお住まいの市区町村の福祉課や清掃課に相談してみましょう。
医療機関
ゴミ屋敷になっているのが、物が捨てられない原因が病気である可能性も考えられます。
特に強迫性障害やためこみ症、うつ病などの精神疾患が背景にある場合は、医療機関の受診をおすすめします。
認知の歪みなどが解消されないと、家の片付けは一時的なものになりがちです。
発達障害等の場合は投薬治療で症状が改善する可能性もあります。
統合失調症などの場合も、適切な薬が合えば症状はかなり早く良くなることもあります。
もちろん薬を飲んだからすぐに片付けができるわけではありませんが、徐々に症状が良くなれば普通の生活が送れるようになるでしょう。
地域コミュニティや福祉
自治体や周辺の方の手を借りることも一つの解決策です。
例えば、夜勤が多くてゴミ出しが難しい人は、ご近所で仲が良い方にゴミ出しだけをお願いするという方法もあります。
もちろんお礼は大切なので、お菓子を渡すなど感謝の気持ちを示すことを忘れないようにしましょう。
また、身体的な障害などがある方は福祉支援サービスを活用できる場合があります。
例えば高齢者向けにヘルパーを派遣して、居住スペースを掃除するサービスなどの利用も検討してみてください。
その他、ゴミ屋敷でお悩みの方が頼れる相談先についてはゴミ屋敷の相談ができない人へ!頼れる相談先と解決までの流れを解説にまとめています。
ゴミ屋敷を放置することで起こる5つの危険性

ゴミ屋敷の状態を放置することは、単に生活が不便になるだけでなく、様々な危険をもたらします。
ここからゴミ屋敷を放置することで起こりうる5つの主な危険性について説明します。
火災発生のリスク
ゴミ屋敷は物が大量にあるだけでなく、ホコリなども多く蓄積しています。
特に冬場など空気が乾燥している時期は、ちょっとした火の不始末や電気系統のショートから火災が発生するリスクが高まります。
コンセントの周りに物が積み重なっていると、熱がこもって発火する危険性もあります。
さらにゴミ屋敷は物が多いため一度火災が発生すると延焼しやすく、消火活動も困難になります。
逃げ道が物で塞がれていると、火災時に避難できなくなる可能性もあり、命の危険に直結します。
また、火災は自宅だけでなく、隣接する住宅にも被害を及ぼすリスクがあり、最悪の場合は賠償責任を問われることにもなりかねません。
深刻な健康被害
換気が不十分で閉め切った環境に、生ゴミが腐敗していたり不衛生な状態が続くと、様々な健康被害が発生します。
カビやホコリが大量に発生することで、喘息や気管支炎などの呼吸器疾患のリスクが高まります。
また、ちょっとした傷から細菌感染を起こしやすくなったり、不衛生な環境で食事をすることで、食中毒になったりするリスクも高まるでしょう。
さらに物が散乱した環境では、転倒などの事故も起きやすく、特に高齢者の場合は骨折などの重大な怪我につながる可能性があります。
害虫・害獣の発生
不衛生な環境はゴキブリやネズミなどの害虫・害獣が発生しやすい条件が揃っています。
ゴキブリやネズミの体に付着している雑菌で食中毒を起こしたり、ネズミに噛まれて感染症を発症する事例もあるので注意が必要です。
さらに問題なのは、発生した害虫や害獣が周辺の家にも被害を及ぼす可能性があることです。
マンションやアパートなどの集合住宅では、隣接する部屋にゴキブリが移動することも珍しくありません。
害虫・害獣の発生源が自宅だと特定された場合、近隣住民から損害賠償を請求されるリスクもあります。
ゴキブリが発生することで近隣に与える被害について近所の家がゴミ屋敷!ゴキブリやネズミが出たときの対策や相談方法を解説でも紹介しています。
近隣トラブルの発生
ゴミ屋敷が原因で近隣住民とトラブルになるケースは非常に多いです
悪臭や害虫の発生は、直接的に周囲の生活環境を悪化させる要因となります。
「ゴミ屋敷の隣には住みたくない」という心理から、引っ越しを検討する住民も出てくるでしょう。
先ほど述べた害虫や害獣が隣の家に移動してしまうと、管理会社や自治体に通報されるリスクも高まります。
集合住宅の場合は、家主から退去を勧告される可能性もあるでしょう。
ゴミ屋敷で発生するトラブルについては隣家がゴミ屋敷に?ご近所トラブルに悩む人必見の解決方法で紹介しています。
近隣の方目線の記事ですが、客観的にゴミ屋敷を見るきっかけになるはずなので、ぜひお読みください。
行政からの指導や強制執行
ゴミ屋敷の被害を受けた近隣住民が行政に申し立てることで、公的な介入を受けるケースもあります。
多くの自治体では、初めは口頭での注意や改善勧告などの軽い措置から始まります。
しかし、改善が見られずに放置し続けると、立ち入り調査や改善命令などより強い措置が取られることになります。
最終的には「行政代執行」と呼ばれる強制的な清掃が行われることもあり、その費用は全て本人負担となります。
代執行の費用は数十万円から数百万円にのぼることもあるので、早めの対応が必要です。
代執行については、行政代執行が行われるゴミ屋敷の特徴とは|費用相場はいくら?で紹介します。
捨てられない人がゴミ屋敷から脱出する方法

捨てられない人がゴミ屋敷から自力で脱出することは、不可能ではありません。
ステップ別に、捨てられない人がゴミ屋敷を改善する方法を紹介します。
STEP1:玄関までの動線と作業場を確保する
ゴミ屋敷からの脱出は、まず玄関から部屋の中心部分への通路確保から始めましょう。
この「動線」を片付けの基点とすることで、ものをスムーズに出し入れして片付けを進められます。
最初に玄関前のスペースに大きなブルーシートや段ボールを敷いて、作業場を作りましょう。
次に、玄関から部屋の中心部に向かって、最低でも幅50cm程度の通路を確保します。
この際、高く積み上がった物は崩れる危険があるので、上から少しずつ慎重に移動させましょう。
STEP2:害虫駆除対策をする
ゴミ屋敷状態の部屋では、害虫が発生している可能性が高いので、まず害虫駆除から始めましょう。
くん煙剤を発煙させて、外に出て薬剤が効くのを待ちます。
特にキッチン周り、水回り、暗くじめじめした場所は重点的に処理します。
作業中は必ずマスク、ゴム手袋、長袖長ズボンを着用し、できればゴーグルも使用して、虫や粉塵から身を守りましょう。
ただし、ゴミが積み重なっているような場合は害虫駆除を最初に実施できないことがあるので、殺虫剤を用意して見つけ次第殺虫する方法をとってください。
STEP3:可燃物や生ごみを撤去して捨てる
害虫対策が完了したら、まず腐敗や火災の危険性が高い可燃物や生ごみから処分していきましょう。
そして、明らかなゴミ(食品の空き容器、腐った食品、使用済みティッシュなど)を丈夫なゴミ袋に入れます。
この段階では「迷わない」ことが重要で、明らかにゴミと判断できるものだけを処理します。
生ごみはビニール袋に小分けにして密封し、悪臭や汁漏れを防止し、可燃ゴミは自治体の指定袋に入れ、収集日に合わせて少しずつ出していきましょう。
量が多い場合は清掃局に直接持ち込み、大きなものは粗大ゴミ回収の予約を検討しましょう。
STEP4:ペットボトルなどの不燃物を捨てる
可燃ゴミの処理が進んだら、次は不燃物やリサイクル可能な資源ゴミの分別を行います。
ペットボトル、缶、びん、プラスチック容器などは洗浄して、自治体のルールに従って分別しましょう。
家電製品は家電リサイクル法に基づいて適切に処分する必要があるので、自治体やリサイクルショップに相談するとよいでしょう。
自治体によってはリサイクルステーションを設置している場合もあるので、まとめて持ち込むのも効率的です。
STEP5:必要なものと不要なものを分別する
明らかなゴミを処分した後は、残った物を「必要なもの」と「不要なもの」に分類していきます。
分類のコツはまず「1年以上使っていないもの」「同じものが複数ある」「壊れていて修理する予定がないもの」に分けることです。
判断に迷う物は「保留ボックス」を用意して一時的に保管し、後で改めて検討するようにします。
例えば洋服や靴は試着して、サイズが合わないものや着心地が悪いものは思い切って手放しましょう。
本や雑誌は「もう一度読みたいと思うか」を基準に判断し、情報が古く参考にならないものは処分を検討します。
分類作業は短時間で区切り、休憩を挟みながら少しずつ進めることで、判断疲れを防ぎましょう。
捨てる決心がつかない場合の対処法
思い出の品や捨てるのに迷う物については、無理に捨てる必要はありません。
特に手紙や写真など、一度捨てると二度と取り戻せないものは大切に保管しても良いでしょう。
ただし、量が多すぎて生活の妨げになる場合は、保管方法を工夫する必要があります。
写真はアルバムにまとめるか、スキャンしてデジタル化することで場所を取らずに済みます。
手紙や書類も同様に、スキャンやデジタルカメラで撮影して保存する方法が効果的です。
子供の作品や記念品は、特に思い入れの強いものだけを選び、写真に撮ってから処分する方法もおすすめです。
STEP6:部屋を清掃して必要なものを収納する
不要なものを処分した後は、残した必要なものを適切に収納し、清掃を行います。
まず、床や壁、窓などの表面を丁寧に掃除し、長期間のホコリや汚れを落とします。
特にキッチンや水回りは、カビや細菌の繁殖を防ぐために消毒用アルコールなどで徹底的に清掃しましょう。
必要なものは「使用頻度」に応じて収納場所を決めると、その後の生活がしやすくなります。
よく使うものは手の届きやすい場所に、季節物や稀にしか使わないものは奥や高い場所に収納するのがコツです。
使用頻度に応じた整頓方法を覚えると、ものを取り出すたびに部屋が散らかるという悪循環を断ち切れます。
ゴミ屋敷のゴミを捨てられない方はプロの片付け業者へ依頼しよう

物が捨てられずにゴミ屋敷状態になり、自力での片付けが難しい場合は、専門の片付け業者への依頼を検討しましょう。
ここからは、プロの片付け業者に依頼するメリットを詳しく説明します。
安全かつ確実にゴミ屋敷のゴミを捨てられる
プロの片付け業者は、安全装備と適切な道具を使用して作業を行います。
天井まで物が積み上がった状態や、害虫・害獣が発生している環境でも、安全に対処するノウハウを持っています。
特に腐敗物や危険物の処理、カビや細菌に汚染された環境の消毒など、素人では難しい作業も確実に処理できるのがメリットです。
また、大量のゴミや不用品も、適切な分別と処分方法で効率的に片付けることが可能です。
自治体のルールに従った正しい廃棄方法を知っているため、不法投棄などのトラブルを避けることができます。
ゴミ屋敷へのリバウンド防止策を教えてくれる
プロの片付け業者は単に物を片付けるだけでなく、再びゴミ屋敷に戻らないための具体的なアドバイスも可能です。
依頼者の生活習慣や性格を考慮した、無理のない収納方法や整理整頓のコツを教えてくれます。
例えば、物の定位置を決める、「ワンアクション」で片付けられる環境作り、定期的な見直しの習慣づけなど、実践的な提案が得られます。
また、不要な物が増えないよう、「物を家に入れる基準」の作り方についてもアドバイスしてくれるでしょう。
便利屋サービス21には、整理収納アドバイザー資格を持つスタッフが在籍しています。
一人ひとりのライフスタイル、性格に合わせた整頓アドバイスが可能なので、是非ご相談ください。
ゴミ屋敷住民の心理に寄り添って作業をしてくれる
優良な片付け業者は、物が捨てられない方の心理状態に配慮した対応を心がけています。
無理に物を捨てさせるのではなく、お客様の気持ちを尊重しながら、少しずつ整理を進めていきます。
思い出の品や大切にしているものについては、「捨てる・捨てない」の二択ではなく、写真に撮って記録に残す、一部だけ保管するなど、折衷案を提案してくれることも。
また、心理的な負担を和らげるため、お客様のペースに合わせた作業進行を心がけている業者が多いです。
便利屋サービス21には業界初の心理カウンセラー資格を持つスタッフが在籍しています。
お客様の心理に寄り添ったアドバイスで、今後ゴミ屋敷にリバウンドするリスクを心理的な部分から改善できるようなサポートが可能です。
周囲への配慮もしてもらえる
プロの片付け業者は、近隣住民や周囲の環境への配慮も徹底しています。
作業車両を目立たない場所に駐車する、作業中の物の搬出入を目立たないように行うなど、プライバシーへの配慮があります。
悪臭や害虫の問題がある場合も、近隣に迷惑をかけないよう適切な対策を講じながら作業を進めます。
また、お客様が周囲にゴミ屋敷の清掃をしているとバレたくないという気持ちに寄り添って、深夜や早朝の作業なども対応可能です。
ゴミ屋敷片付け後の清掃作業も依頼できる
片付け後の徹底的な清掃も、プロの業者なら安心して任せることができます。
長期間掃除されていない床や壁は、一般的な清掃方法では落ちない頑固な汚れが付着していることがあります。
プロの業者は業務用の清掃機材と洗剤を使用し、一般家庭では難しい徹底的な清掃が可能です。
特に重要なのは、目に見えない細菌やカビ、ダニなどの除去と消毒作業です。
これらの作業により、健康的で清潔な生活環境を取り戻すことができます。
便利屋サービス21で対応した「捨てられない」お悩みの解決事例

両親が高齢になったことで不用品を溜め込むようになってしまった実家の片付け【埼玉県上尾市】
埼玉県上尾市のお客様より、高齢の両親が「捨てられない」ため、お部屋を片付けて欲しいとの依頼を受けました。
若い頃は綺麗好きだったそうですが、年齢を重ねるごとにお部屋に不用品が溜まり、片付けられない状態になってしまったそうです。
このままでは転倒による怪我のリスクもあるということで、早急にお見積もりに伺うことに。
高齢のご両親に負担がないように、スタッフ3名で1時間という短時間で、不用品を回収することとなりました。

最初はこのような状態だったお部屋が、見違えるように。

短時間で不用品を回収してすっかり部屋が綺麗になり、「こんなに短い時間でありがとうございます」と感謝の言葉をいただきました。
ゴミ屋敷のゴミを捨てられない方向けのよくある質問

物が捨てられずにお悩みの方々から、当社によく寄せられる質問とその回答をご紹介します。
片付けを検討される際の参考にしていただければ幸いです。
ゴミ屋敷の片付けにかかる期間は?
片付けにかかる期間は、部屋の広さやゴミの量、状態によって大きく異なります。
一般的な1DKのアパートで床から天井まで物が積まれている場合、プロの業者なら2〜3日程度で作業が完了することが多いです。
一方、一戸建ての場合や特殊な状況(害虫の大量発生、腐敗物の処理が必要など)では、1週間以上かかることもあります。
自力で片付ける場合は、仕事や体力との兼ね合いで、数週間から数ヶ月かけて少しずつ進めるのが現実的です。
ただし、間取りが1LDK以上やゴミの量がかなり多い場合は、自力での対処は難しいので、業者へ依頼した方が良いでしょう。
ゴミ屋敷の片付け費用の相場はどのくらい?
片付け費用は、部屋の広さ、ゴミの量、状態によって変動します。
一般的な相場として、1DKの場合で15万円〜30万円程度、2LDKで30万円〜50万円程度となることが多いです。
特に考慮すべきは害虫・害獣の駆除が必要かどうか、特殊清掃(腐敗物、排泄物など)が必要かどうか、家具や家電の処分が含まれるかどうか、作業後の消毒・消臭が必要かどうかなどがあります。
複数の業者に見積もりを依頼して、サービスの内容と費用が適切な業者を選びましょう。
一人でゴミ屋敷を片付けるのは可能?
基本的には可能ですが、以下のような場合は業者への依頼をおすすめします。
天井まで物が積み上がっている場合は、崩落の危険があり素人では安全に作業できません。
害虫や害獣が大量に発生している環境は、健康被害のリスクが高く専門的な対処が必要です。
高齢の方や体力に自信のない方は、重い物の移動や長時間の作業で怪我をするリスクがあります。
時間的な制約がある場合(例:賃貸契約の終了が迫っている、近隣からの苦情で急ぎの対応が必要など)も業者の方が早く片付くので安心です。
ゴミ屋敷の再発を防ぐコツは?
ゴミ屋敷へのリバウンドを防ぐには「物を持ち込まない」原則を徹底し、新しい物を購入する前に「本当に必要か」「置く場所はあるか」を考える習慣をつけましょう。
「ワンイン・ワンアウト」のルールを設け、新しい物を買ったら同じカテゴリーの古い物を一つ処分する習慣も効果があります。
毎日少しずつ掃除や整理をする時間を設け、例えば「1日5分だけ片付ける」といった小さな習慣から始めましょう。
困ったときに相談できる人を確保し、一人で抱え込まない環境を作っておくことも再発防止に効果的です。
物への執着が強い場合は、認知行動療法などの心理療法を受けることも検討してみてください。
まとめ:ゴミ屋敷の不用品を捨てられないなら便利屋サービス21へ
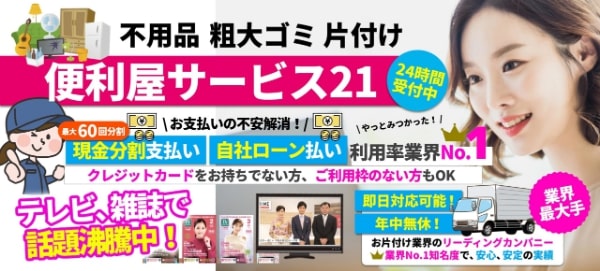
物が捨てられずにゴミ屋敷状態になってしまった場合、無理に自力で解決しようとせず、専門家の力を借りることも検討しましょう。
便利屋サービス21では、物が捨てられないお客様の気持ちに寄り添いながら、丁寧かつ確実な片付けサービスを提供しています。
当社では、お客様のプライバシーを最大限に配慮し、周囲に気づかれないような配慮も徹底しています。
また、単なる片付けだけでなく、再発防止のためのアドバイスや定期的なフォローアップも可能です。
まずは無料相談から始めることができますので、一人で悩まず、ぜひ便利屋サービス21にご相談ください。