「遺品整理をしなくちゃいけないけど、いつ始めれば良いんだろう…?」
「遺品整理を進めたらダメな時期、遺品整理を終えなければいけない期限ってあるの?」
この記事では遺品整理を始めるのに最適なタイミングと、タイミングを選ぶ際の注意点について解説しています。
また、時期を決めるのに参考となる、遺品整理に必要な日数や流れについてもご紹介します。
この記事を読めば、自分にとって最適な遺品整理を始めるタイミングが分かるようになります!
目次
遺品整理を始めるのに最適な6つの時期

遺品整理は絶対にこの時期にしなければいけないという時期はありません。
しかし、よりスムーズに遺品整理を進めたいなら、最適な時期が6つあります。
葬儀直後(7日前後)
亡くなってから7日前後、葬儀が終わった直後が一つ目の遺品整理に最適な時期です。
この時期に遺品整理を終わらせられると、健康保険や年金など期日のある手続きも漏れなく終わらせることができます。
また、レンタル品の返却やサブスクリプションの解約など費用の支払いが発生するようなサービスも早々に利用停止できるため、損失を少なくすることができます。
諸手続き後(14日~)
葬儀が終わっても様々な手続きがあったり、亡くなった方の知り合いと連絡を取ったりと忙しい日々が続くことがあります。
その場合には、諸手続きが終わり連絡も落ち着く、14日以降に遺品整理を始めるのがおすすめです。
賃貸の部屋の場合、亡くなってから1、2ヶ月以内に退去するのが一般的です。
退去が遅くなるほど賃貸料が発生するため、1ヶ月以内に退去したいという方はこの14日〜1ヶ月以内に遺品整理を終わらせる必要があります。
49日前
宗教にもよりますが、亡くなってから49日目に49日法要という法要を行います。
葬儀が終わり、次に親族で集まるのがこの49日法要だという場合は、49日前に遺品整理を終わらせておくと形見分けなどがスムーズです。
【関連情報】
▶遺品整理は49日前に終わらせるのがおすすめ!メリットと注意点を解説
相続税申告前(~10ヶ月)
一定以上の資産を相続した場合、相続税という税金が発生します。
相続税についての申告は、亡くなってから10ヶ月以内にしなければいけません。
そのため、預貯金、不動産、宝石など高額な資産になりそうな物はこの時期までに把握し、だれがどのように相続するかを決めておく必要があります。
この10ヶ月前を目安に遺品整理をする方も多くいらっしゃいます。
相続税については国税庁の『No.4155 相続税の税率|国税庁』で詳しくご覧頂けます。
また、相続税についてお悩みの場合はお近くの税務署か、税理士事務所にご相談がおすすめです。
新盆・一周忌など法要の前
新盆や一周忌など法要で親族が集まる前に遺品整理を終わらせておくのもおすすめです。
形見分けがスムーズになるというメリットだけでなく、遺品整理で見つけた想い出の品などを手に、皆で亡くなった方の思い出話をすることが良い供養となります。
気持ちの整理がついた時・つけたい時
どうしても気持ちの整理がつかない時に、無理に遺品整理を始めても、上手く進まなかったり、後悔が残ったりしてしまいます。
この場合には、気持ちの整理がついたときや、つけたいと思えた時に遺品整理を始める方が良いでしょう。
注意!遺品整理が遅れることで生じるコスト・リスクがある

遺品整理自体には決められた期限はありませんが、期日のある手続きや、賃貸料金など遺品整理が遅れることで生じるコスト・リスクがあります。
その中でも影響の大きいコスト・リスクを5つ解説します!
家賃や固定資産税の支払い
遺品整理の時期を遅らせると、部屋の退去や物件の売却も遅くなってしまいます。
その分、賃貸なら家賃が、持ち家なら固定資産税が発生してしまうので注意が必要です。
固定資産税は、毎年1月1日に所有している人に支払い責任が生じます。
(参考:固定資産税・都市計画税(土地・家屋) | 税金の種類 | 東京都主税局)
しかし、売却した際は売主と買主で固定資産税を日割りにし、それぞれ負担するのが一般的です。
そのため、持ち家であっても早めに遺品整理を終わらせ、売却した方がお得になります。
便利屋サービス21では売却までサポートさせて頂くプランもありますのでお気軽にお問い合わせください。
【実家の片付け・空き家OK】不動産売却から売却に伴う片付け|便利屋サービス21】
年金や税金など必要な手続きの不足
年金の受給停止や、健康保険の資格喪失、相続税についてなど、人が亡くなった時にはしなければいけない手続きがあります。
遺品整理が遅くなると、必要な手続きが何かわからず、不足してしまうことがあるため注意しましょう。
例えば、年金を受け取っていた場合、国民年金は14日以内に、厚生年金は10日以内に手続きが必要です。
手続きをせず、亡くなった後も年金を受給してしまった場合は、返還手続きが必要になってしまいます。
詳しくは以下のページをご覧ください。
▶年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構
国民健康保険に加入していた場合は、14日以内に資格停止手続きが必要です。
自治体によっては、死亡届を提出した時に自動的に手続きが行われるところもあります。
(参考:被保険者が亡くなられた後の手続き一覧 台東区ホームページ)
役所に死亡届を提出した際に、必要な手続きについて確認しておくと安心です。
不用品の処分費用の増加(不用品買取額の減少)
不用品の処分には費用がかかります。
燃料費や物価の上昇などにより、遺品整理を遅らせたことで不用品の処分費用が増加することがあります。
実際、各自治体の粗大ゴミ収集の値段も上がっています。
令和5年10月1日には、東京都23区の粗大ゴミ処理手数料が値上がりしました。
値上がり幅は物によって異なりますが、幅と高さの合計が360センチ以上のタンスの場合だと、400円も値上がりしています。
(参考:令和5年10月1日から粗大ごみ処理手数料が変更になります)
また、不用品買取を利用する場合は買取額が少なくなってしまうケースもあります。
一般的には、古くなれば古くなるほど物の価値が下がってしまうからです。
特に家電などはその傾向が高いため、買い取ってもらえなくなることもあります。
悪臭・害虫・火災などの発生
遺品整理をせずにそのままにしていると、悪臭や害虫、火災などが発生するリスクがあります。
特にゴミ屋敷の場合はリスクが高いため、要注意です。
ゴミ屋敷ではない場合も、誰も住んでいない実家を売却せず空き家にしておくと、放火や犯罪に使われてしまう危険性があります。
精神的ストレス
遺品整理に手を付けないでいると、人によっては遺品整理をしなければというプレッシャーを感じることがあります。
そのプレッシャーが精神的ストレスになってしまう場合には、早めに遺品整理を終わらせた方が良いでしょう。
遺品整理にかかる日数の目安

遺品整理を始めようと思った時に気になるのが、遺品整理にかかる日数です。
部屋の状況や片付けが得意かどうかなどにもよりますが、目安をご紹介します。
自分でする場合:1週間~
遺品整理を自分で進める場合、1週間以上見積もっておいた方が良いでしょう。
急げばもっと早くできるかもしれませんが、自分1人で終わらせるにはこまめに休憩をし、無理しないことが大事です。
一度にたくさん進めようとすると限界まで動いてしまいやすいので、まずはその日にどこを整理するのか計画を立ててから始めるのがおすすめです。
身内に手伝ってもらう場合:2、3日~
手伝ってもらえる人が多くいれば、手分けして2、3日で終わらせられることもあります。
しかし、大型の家具や家電の処分には注意が必要です。
自治体の粗大ゴミ回収や不用品回収業者は、すぐには回収に来れないことがあります。
そのため、2、3日で遺品自体の整理は終わっても、不用品回収が終わらないということもあるでしょう。
部屋の退去や物件の売却など期限がある場合は、先に不用品回収の予定を確認しておくと安心です。
業者に依頼する場合:1日~2日
遺品整理の専門業者に依頼すると、1日~2日で遺品整理を終わらせてくれます。
不用品回収も可能な業者に依頼すれば、遺品整理と同時に不用品の搬出なども終えてくれるため、すぐに部屋の退去や物件の売却が可能です。
遺品整理の流れ

実際に遺品整理をする場合、以下の流れで進めます。
自分でする場合/身内に手伝ってもらう場合
自分でする場合、身内に手伝ってもらう場合には以下のような流れで遺品整理を進めましょう。
- スケジュールを調整する
- 必要な道具を準備する
- 遺品を整理する
- 掃除をする
- ゴミや不用品を処分する
身内に手伝ってもらう場合特に重要なのが、スケジュール調整です。
可能であれば何日か余裕をもって調整しておくと、焦らずに遺品整理を進めることができます。
また、どんな物を保管し、どんな物を処分するかのルールを統一しておくことも重要です。
業者に依頼する場合
遺品整理を業者に依頼する場合は、以下の流れで進めます。
- 業者を探す
- 相見積りをとる
- 業者に依頼する
- 業者と一緒に遺品整理をする
遺品整理自体は遺品整理業者が段取りをつけてくれるため、業者にお任せできます。
また、忙しかったり、遠方だったりで遺品整理に立ち会えない場合、業者だけで進めてもらうことも可能です。
遺品整理を自分でする方法

遺品整理を自分でする場合、以下の7ステップで進めていきます。
- 事前に手続きや退去日などの期日を確認しておく
- スケジュールを決める
- 不用品回収・買取など必要な業者の手配をする
- 道具を準備する
- 遺品を仕分けする
- 仕分けした遺品をそれぞれ分配・売却・処分する
- 部屋の清掃を行う
詳しい内容については以下のコラムにまとめられています。
▶【7ステップ】自分で遺品整理をする方法と注意点を徹底解説!
遺品整理を業者に依頼するなら便利屋サービス21がおすすめ!
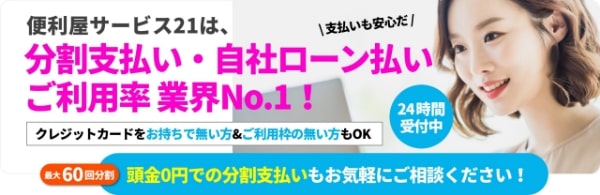
遺品整理を業者に依頼する時に悩むのが、どの業者に依頼するかです。
遺品整理のタイミングでお悩みの方におすすめしたいのが、便利屋サービス21です。
即日対応可能で必要なタイミングに合わせられる
便利屋サービス21は即日対応可能なため、お客様の必要なタイミングに合わせて遺品整理を終わらせることができます。

- 作業内容:遺品整理と不用品回収
- 作業時間:一日以内
こちらは公式LINEからお問い合わせ頂き、翌日にお伺いして遺品整理をお手伝いさせて頂いたご依頼です。
海外転勤を控えていたお客様は、転勤前に供養できたことでとても安心されたご様子でした。
遺品整理専門アドバイザーがサポート
遺品整理には、遺品整理士、特定遺品整理士という専門の資格があります。
法規則を遵守して遺品整理を進めながらも、亡くなられた方の想い、遺された方の想いに寄り添うことができる専門家の証です。
便利屋サービス21には遺品整理士、特定遺品整理の資格をもった専門アドバイザーが在籍しています。
遺品整理に不安やお悩みがある方も安心してご依頼ください。
後払い・分割払い利用で頭金0円でご依頼可能
遺品整理を始めたいと思ったその時、経済状況のタイミングはあまり良くないことがあります。
そんな時には頭金0円でご依頼頂ける便利屋サービス21がピッタリです。
後払い・分割払いが可能ですので、安心してお問い合わせください。
相続放棄する場合の注意点
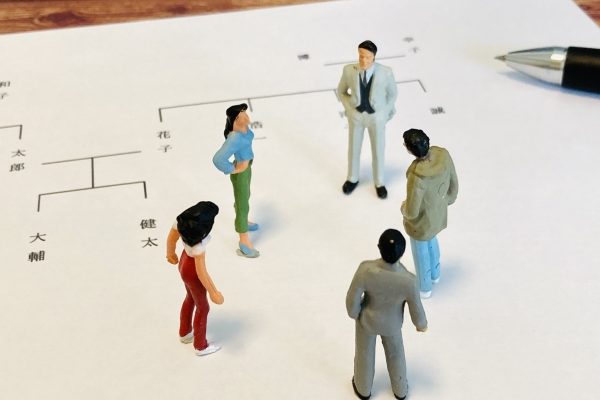
人には様々な事情があり、中には相続を放棄したいという方もいらっしゃいます。
相続の放棄は認められている権利ですが、相続放棄する場合には注意が必要です。
相続放棄の手続きができるのは3ヶ月以内
相続放棄には手続きが必要です。
相続放棄の手続きができる期間は、亡くなった人から自分に相続される資産があると知ってから3ヶ月以内とされています。
手続きは家庭裁判所で行います。
(参考:相続の放棄の申述 | 裁判所)
遺品整理をしてしまうと相続放棄できないことがある
遺品整理をすると、遺産を管理する意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
相続放棄を考えている場合には、遺品整理はしないようにしましょう。
まとめ:遺品整理は自分に合ったタイミングで!出来れば早い方がおすすめとする

遺品整理に最適な時期には、以下の6つがあります。
- 葬儀直後(7日前後)
- 諸手続き後(14日~)
- 49日前
- 相続税申告前(~10ヶ月)
- 新盆・一周忌など法要の前
- 気持ちの整理がついた時・つけたい時
しかし、遅らせるとリスクやコストが発生してしまうため、出来れば早い時期に終わらせるのがおすすめです。
便利屋サービス21なら即日対応、頭金0円でのご依頼が可能ですので、お客様にとって最適なタイミングで遺品整理を終わらせるお手伝いができます。
是非お気軽にお問い合わせください。












































